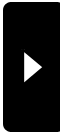徒然雑感今帰仁の面影グスク時代
”ヤマタイカ” がヒットした
作者は ”星野之宣”
海洋博が開催されていた頃に”ブルーシティー” を週刊少年ジャンプに連載していた作者だ
”アクアポリス” に類似した研究所や ”エラのある水棲人類” が出てくるSF漫画だった

”ヤマタイカ” は
久高島の神女(ノロ)を中心とした集団が
日本全土を巻き込み日本古代の祭祀(マツリ)の復活を通して
未来へ向けた新しい遺産を創造していくいわば”現代の創世神話”なのだろう
日本画を学んだという作者の画風はシュールで展開も早く時間を忘れ読むことができた
ヤマタイカを読んでいてあの頃に週刊少年ジャンプに掲載されていた ”ブラフマン” ・”アートマン” を思い出した
”諸星大二郎” の ”暗黒神話” だ
作画のタッチは異様で作品の内容と相まって何か不安に陥れられるような画風だった
(水木しげる 楳図かずお エコエコ・アザラク風? 日野日出志)
まだ小学生だった自身は複雑な内容は理解できず怖々とみてたのがとても印象に残っている
”ヤマタイカ” は現在絶版のようでジュンク堂も扱いはなかった
中古品でも全5巻で1~2万円と結構な値段がついている(レジェンド・オブ・ヤマタイカ)
AMAZONのKindleでは1巻数百円・・・・Kindleで初めて購入しiPadで閲覧した
ジュンク堂では
作家別の作品コーナーがあり星野之宣と諸星大二郎は同じ列に入っていた
諸星の方は ”暗黒神話” と読んだことのない姉妹作だという ”孔子暗黒伝”
それに ”稗田礼次郎シリーズ” の ”妖怪ハンター” を購入(いずれも文庫版だった)
”ヤマタイカ” のキーワードの一つに ”オモイカネ” がある
孔子暗黒伝にもオモイカネはでていた
また両者に ”万座毛” の描写もあった
”オモイカネの神” は日本神話で知恵を司る神だという
”オモイカネ” は ”思金・思兼” の漢字が当てられる
・・・・なんと琉球風というか ”うちなぁ” だった
GWは天気が良かったのは5月3日のみ
その他は小雨混じりの曇り空か雷雨で久々のコミック三昧だ
追記)
琉球の開闢神話の中の ”天孫氏”
その王統は約17800年25代続いたとされています
天孫氏の最後の王は ”思金松兼”
また第二尚氏時代に編纂された ”球陽外卷・遺老説伝” の説話・民話集第68話に ”黄金の瓜子(うりざね)” があり久高島の少年 ”思松兼” の説話が収録されています
思松兼は英祖王統第4代 ”玉城王” 側室の男子だとされています
また思松兼は他の民話などにも登場しているようです;複数いる?
”ヤマタイカ” では
古代の祭祀に用いられた巨大な銅鐸”オモイカネ” の小さな雛形”オモイマツカネ” が古代船とともに久高島が望める現:南城市の”斎場御嶽” に秘匿されていたことになっています
また作中では ”祭” に ”マティ” とルビが振られていました
(御祭:ウマチー)
個人的には
辺戸岬から到来した ”天孫氏” は ”平維盛”
久高島から玉城百名に到達した ”アマミキヨ(アマミク)” は ”平資盛”
・・・・の兄弟・・・・なのかなと妄想しています
”天孫氏” の集団は ”今帰仁世:うちなぁ” を
すこし遅れた ”アマミキヨ” の集団は ”英祖王統” となった ?
”東の海” の向こうに私たちのルーツはきっとあると思います